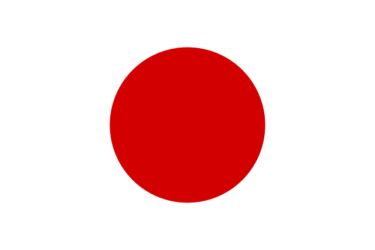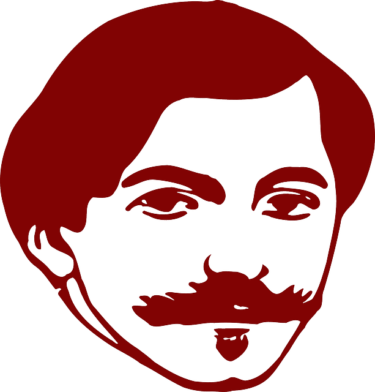どうも、武信です。(No114)
英語の民間試験採用が、延期すると発表されました。
以下の記事を貼ります。
https://dot.asahi.com/aera/2019110100080.html
「英語民間試験の問題は「公平性」だけではない 「中止を」約7割が支持〈AERA〉」というタイトルです。
簡単に、引用・まとめをします。
「ぼくたちに入試を受けさせてください」と訴えたのが、筑波大学附属駒場高校(筑駒(2年生の男子生徒(17)です。
共に、文部科学省前のデモや国会でのヒアリングなどで、当事者となる高校生の声を届けてきた私立高校2年生の健さん(17)は教員志望の人です。
公平性を重要視していない、萩生田大臣の発言「自分の身の丈に合わせて(試験)を選んで勝負して頑張ってもらえれば」に非難が集中し、「教育基本法」に抵触するとの声も上がっていたそうです。
異なる試験の成績を対応させるため、導入された共通指標『CEFR(セファール)』の活用自体にも問題があり、公正ではないといいます。
英語民間試験の実施について延期を求める声が約2割、中止を求める声が約7割で、「どうしても4技能の試験をしたいなら入試センターが統一テストを作るべきだ」という45歳の女性の保護者の意見もありました。
「大学入試センターが主導して、民間と専門の研究者の知恵と技術を合わせながらスピーキングの統一テストを開発すべき。
本気で取り組めば2024年度実施も不可能ではありません」ともあります。
以上、ここまで。
これらの意見に対し、僕が思っていることを述べていきます。
1 そもそも大学入試は平等ではない。
まず、「大学入試は公平であるべきだ!」と多くの人が思っているようですが、そもそも論として完全に平等であるわけがありません。
以下の記事があります。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/09/6950.php
「東大生の親の6割以上は年収950万円以上」というタイトルです。
簡単に引用・まとめをします。
<東大をはじめとした有力大学に入るには、幼少期からの塾通いや私立一貫校への進学など多額の教育投資が求められる>
大学生の家庭の平均年収は830万円で、国立は841万円、公立は730万円、私立は834万円だ。
年収1000万円以上の割合は国立が29.2%、公立が20.3%、私立が25.7%となっている(日本学生支援機構『学生生活調査』2016年度)。とあります。
東大生の親の62.7%が年収950万円以上だ。
一般群では12.3%しかいないことを考えると、極めて高い比率と言える。
職業をみると東大生の父親の43.4%は管理職で、こちらも一般群(3.6%)とは大きな隔たりがある。
現在は、個人の能力が重視される業績主義の時代で、「生まれ」がモノをいう属性主義は否定されている。
しかしそれは形式上のことで、実際には後者が生きながらていることがしばしばある。
上記のデータを単なる偶然と解釈する人はいないだろう。とあります。
もっと詳しい入試の不平等については、記事をお読みください。
つまり、有力大学に受かるには「親の経済力」か、または「遺伝的要素(地頭など多数)」が良くないと入れないのが、リアルな現実というわけです。
そもそも大学入試なんて、全然、平等じゃなかったのです。
英語の民間試験で、貧困層には費用面で補助すると言っているのに無視され、『CEFR(セファール)』の活用自体に無理があるのは一理あるとしても、そもそも大学入試自体が根本的に平等ではありません。
2 そもそも大学入試は平等ではない2
続きです。
以下の記事を貼ります。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68206
「萩生田大臣「身の丈」発言を聞いて「教育格差」の研究者が考えたこと」というタイトルです。
以下、一部、引用・まとめをします。
2020年度実施の大学入学共通テストの概要が紹介され、新しく導入される民間英語試験によって受験生の間に「格差」が生じるリスクが取り上げられました。
シンプルに言えば、費用の異なる民間英語試験を2回まで受けることが可能という制度設計や、試験会場が満遍なく準備されていない状況が「不公平」を生むという指摘です。
経済的に恵まれていない家庭では試験の受けられる回数も減るだろうし、試験会場から遠方の地域に住む受験生は試験を受けづらいというわけです(交通費の負担も大きくなります)。
大臣はこう反論しました。
「そういう議論もね、正直あります。ありますけれど、じゃあそれ言ったら、『あいつ予備校通っててずるいよな』というのと同じだと思うんですよね。
だから、裕福な家庭の子が回数受けて、ウォーミングアップができるみたいなことは、もしかしたらあるかもしれないけれど、そこは、自分の、あの、私は身の丈に合わせて、2回をきちんと選んで、勝負してがんばってもらえば」
試験会場が少ない地方の受験者に不利であるという点については、会場追加を試験団体に依頼していると言及した上で、「だけど、人生のうち、自分の志(こころざし)で、1回や2回は故郷(ふるさと)から出てね、試験を受ける、そういう緊張感も大事かなと思うんで」と述べました。
これらの発言に対してインターネットでは強い反発が渦巻き、野党も注目。大手メディアは批判的な論調で報道しました。
略。
今後は1年かけて民間試験の活用有無も含めて制度を再検討し、2024年度からの実施を目指すということです。
好意的に大臣の発言の意図を汲み取ると以下になります。
「現状でも予備校などによって教育機会の格差がある。これくらいの制度変更は「身の丈」にあった準備・努力をして、よい結果を出せばいい。それくらいのことはできるはずだ。若者よ、逆境を乗り越えていけ!」
しかし、「生まれによる格差」は乗り越えられないといいます。
日本の教育における不公平さ、「教育格差」の実態は克服できるレベルじゃないのです。
詳しくは「教育格差」という本に、データを基に様々な視点で論じているようです。
戦後日本社会はいつの時代も、「出身家庭」と「出身地域」という、本人が選んだわけではない「生まれ」によって最終学歴が異なる教育格差社会です。
データは、出身家庭と出身地域という「生まれ」による教育格差が戦後すべての世代・性別に存在していることを明確に示しています。
しかし一方で、経済的に恵まれない家庭や地方の出身であっても、大学に進学し卒業して、親と比べて社会的地位の上昇を果たした…そんな知り合いを思い浮かべるのは、それほど難しくはないでしょう。
もしかしたら、これを読んでいるみなさん自身が、このケースに当てはまるかもしれません。
2015年時点の20代(1986~95年生まれ)男性において、「父親が大卒」の場合、その80%が大卒になりました。
一方、「父親が大卒でない」場合は、本人が大卒となる割合は35%にとどまります。
父親の学歴という粗い分類だけで明らかな格差が確認できるのです。
大きな格差ではありますが、裏を返せば、「父親が大卒でない」場合でも本人が大卒になったという人が35%はいることになります。
これほど大きな格差ではないですが「出身地域」でも格差は確認できます。
大都市圏や大都市部出身だと大卒となる傾向があるのです。
たとえば、先ほどと同じ年齢層の男性だと、大都市出身だと63%、郡部出身だと39%が大卒になりました。
もちろん、地方出身でも大卒になる人たちはいますが、それは同じ地域出身の中では少数派ですし、地方の中で相対的に有利な出身家庭の人が大卒になる傾向があります。
出身家庭の有利・不利を示す「社会経済的地位(SES)」という指標があり、このSES指標が高いと高学力であることが知られています。
しかしやはり、少子化とはいえ日本は人口規模が大きいので、相対的貧困層の出身であっても高学力の子を実際に見つけることは、そんなに難しくありません。
具体的には、近年の子供の人口規模は1学年120万人前後なので、出身家庭のSESが下位16%の層であっても、そのうちの1.2万人ぐらいは高学力(偏差値60以上)です。
同じく家庭のSESが下位16%で高学力ではない約18万人を無視し、何らかの理由で高学力となった1.2万人だけに視線を注げば、「日本は教育格差を乗り越えられる社会だ」と思い込むことができます。
略。
実は、2020年度実施の大学入試改革は、すでに存在する教育格差を拡大すると考えられます。
私が限られた紙面で以下お伝えできるのは、とても単純な「傾向」です。
そもそも志・能力・努力は、出身家庭によって大きく異なります。
両親が大卒であると、大学進学を具体的に想定し、学力は高く、長時間学習努力をする傾向にあります。
たとえば、中学1年生時点で明確に大学進学を期待する生徒は両親大卒だと60%、親のうち1人が大卒だと41%、両親が2人とも非大卒だと23%です。
この「意欲」格差の背景には、学校外の習い事などを含む、出身家庭による教育経験の蓄積量の差があると考えられます。
学力も、小学校入学時点で親の学歴による格差があります。
また、親の学歴によって子育て戦略に差があり、小学校4年生から「学校外学習時間」の格差は拡大します。
これらの格差はすべて学校間・地域間でも確認できます。
前述した「生まれ」の状況を示す指標であるSESが高い地域であることを背景に、大学進学を目指すこと、学力が高いこと、学習努力をすることが「規範」となっている学校があります。
一方、小学校であっても、恵まれない地域では、大学進学を目指す児童の割合が低く、学力も低く、学校外学習の時間まで短いことが「ふつう」である学校があるのです。
大学進学意欲を持つ、一定以上の学力に達する、努力することが「当たり前」になるという受験競争で実質的なスタートラインに立つための条件を誰もが持っているわけではないのです。
意欲も学力も学習時間も目には見えません。
子供たちは視界に入る同級生を基準にして自分が「ふつう」なのかを判断しているはずです。
しかし、小学校や中学校といった狭い範囲で「ふつう」なことは、大学入試のような全国区の競争の中での「ふつう」を必ずしも意味しません。
出身家庭のSESや出身地域によっては、目に見えない障壁が数多くあり、結果として大学進学に至らないと考えられるわけですが、今回実施が予定されていた入試改革はそんな障壁をさらに増やすことになります。
センター試験に比べれば明らかに試験制度は複雑です。
どの民間英語試験をいつ受けるのか、どの大学・学部がどの程度重視するのか、国語・数学の記述式問題で高得点を取るための手法の練習など、選択肢が増えるといえば聞こえはいいですが、ゲームのルールが複雑になると、親、親戚、予備校や家庭教師、進学校といった様々な「支援者」から、上手く立ち回るための援助を受けることができる生徒ばかりが有利になるでしょう。
もともと大学進学意欲を持ちづらい家庭環境・地域の生徒は、そこまでして大学に行かなくてもよい、と「自発的」に受験そのものを諦めたり、背伸びして有名大学を狙う必要はない、と選抜度の低い大学を「志願」したりするようになるかもしれません。
試験制度を単純化し、基準を明確にして筆記試験による選抜にすれば、高SES層の有利さは減ると考えられます。
もちろん、高SES層は未就学段階から様々な教育的刺激を受けて育っているので、この層が有利なことに変わりはありません。
筆記試験による苛烈な受験競争が話題になった1980年代あたりに大学受験を経験した世代であっても、出身家庭のSESと最終学歴には明快な関連が確認できます。
「生まれ」が最終学歴に変換される経路は数多くあるので、後はどの程度の家庭・地域の有利さ・不利さを社会として許容できるのか・できないのか、という価値判断の問題になります。
では、今回の入試制度改革は、制度を複雑化することで目に見えない障壁を増やし、低SES層と地方出身者を自発的に諦めさせるという代償を払うほど価値のある便益を、一部、あるいは全体にもたらすのでしょうか。
当面は延期になった民間英語試験、それに、国語・数学の一部に記述式問題を予定通り導入したところで、学生が英語を話すことができるようになる、採点可能な範囲の記述式問題の対策をすることでモノを考えることができる、そのような結果を支持する研究はどこにあるのでしょうか。
略。
私が最も気になるのは、制度を変更する前に、きちんとした「データ取得計画」が作られていないことです。
これは「改革を実行する」こと自体が目的であって、そもそも効果を検証するつもりがないことを意味します。
こうした点を自覚的に変えない限り、今回の入試改革もまた、戦後日本の教育行政で繰り返されてきた「改革のやりっ放し」になります。
おそらく今回の改革についても、制度変更の後、早くて数年後に研究者が工夫して、低SES層と地方出身者に不利な「改革」だったという実証知見を提出することになると思います。
その頃には、制度変更によって不利益を受けた生徒たちは成人となり、変更がなければ受けていたかもしれない教育機会を喪失したまま、人生100年時代を生きていくことになります。
「身の丈」に合わせてしまったせいで、低SES家庭の生徒・地方出身者が、自身の可能性を追求できないことは、社会としても非効率です。
ただでさえ少子高齢化で子供の数が減っているわけで、恵まれた家庭出身・都市部出身者の中「だけ」から各分野を将来牽引する人たちが出てくることを期待するのは、とても効率が悪いわけです。
低SES家庭・地方在住の子供たちが直面する有形無形の経済的・文化的障壁を可能な限り取り除き、一人でも多くの子供たちが挑戦する教育的価値のある選抜試験に向かって切磋琢磨することこそが、この社会を強化します。
今回の制度変更は、この方向の真逆に向かっていく「改革」です。以上、ここまで。
長めに引用・まとめをしました。
かなりの良い文章ですし、この文章についてきちんと後で反論や意見を言いたいので、引用させてもらいました。
この文章の内容をしっかり頭に入れてから、PART2以降をお読みください。
2020年教育改革への僕の本「英語の民間試験採用の延期について」PART2
ではこの辺で。(6232文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。 「教育格差」