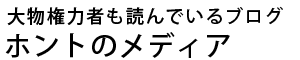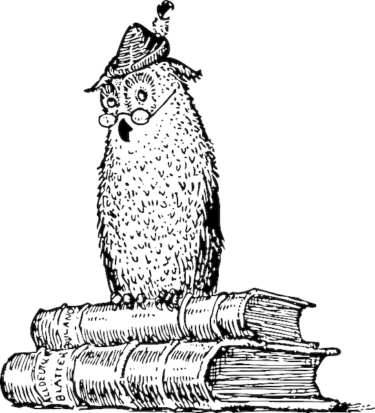どうも、武信です。(No146)
前回の記事が以下です。
2020年教育改革への僕の本「フィクサーによる日本の教育改革本5 第3章 下」PART3です。
構想約5年以上!総文字数約31万2000文字以上の執筆物です。
フィクサーだと僕が思う理由は、2014年頃(正確には2013年頃から着手)から、この本を書き始めており、それと連動して日本の教育改革も進んだことが、まず挙げられます。
また、それ以上の確固たる証拠もありますが、それは伏せることにします。(本が1冊書けるほどの情報量になります)
10 日本は何で食っていくか?と教養について
さて、「日本は何で食っていくか?」という視点が抜けていないでしょうか?
「教養や学問(文系ね)」で日本人の大半は食っていけるのでしょうか?
学者や大学受験信奉者は、大局観が抜けていると考えています。自分たちの視点からしか見ていません。
自分たちが教養や学問で食っていて、他の人たちに押し付けようとしていることに気づいてない人もいます。
「未来予測の超プロが教える本質を見極める勉強法」からの引用・まとめです。
欧米の大学では一般教養教育こそが大学の本流であって、「専門教育は一種の職業訓練にすぎない」と考えられています。
一般教養教育のほうが重要であるのは、将来どのような職業に就くにしても、「人文科学、社会科学、自然科学の三分野の知識を幅広く習得するのが不可欠である」という前提に立っているからです。
これは「一般教養課程よりも専門課程が格上である」と考える日本の大学教育とは大きく異なります。以上、ここまで。
欧米では教養は重要視されているようです。
教養はあるに越したことはないです。
G型で食っていく人たちは、なるべく身につけた方がいいでしょう。
しかし、G型といえど教養はなるべく手っ取り早く学びたいものです。
知識面の教養は本やネットなどで十分ではないでしょうか。
今、議論されている人文科学・社会科系の国立大学廃止論(文科省は行き過ぎた発言だと謝罪)は、「人文科学は私立がやればいい」という話でしょう。
教養はあるに越したことはありませんが趣味レベルの話です。
確かに教養はグローバルでの交渉や人間関係を築くときに有利です。
繰り返しますがグローバル展開したとき、その国の歴史と宗教と文化は必須学習項目です。
それ以外の教養(哲学や文学など)は趣味です。
G型でビジネスをする場合、欧米人を相手にするなら教養(特に、日本の歴史などを語れること)は大事です。
ちなみに、L型は技術職系(手に職系)なのでそもそも教養に不向きであり、習得しにくいでしょう。
L型は国内が主であるし、海外からの外国人客相手に教養が必要になる場面が少しあるぐらいであり、基本的に不必要だと言えます。
教養についての是非は、「「読まなくてもいい本」の読書案内」が参考になります。
著書の橘玲氏は旧来の経済学、哲学、心理学、社会学、政治学、法学などは10年もすればまったく別のものになると言っています。
そして、これらの学問は時代遅れであり、新しいパラダイムに対応していないそうです。
著者のタイトルの通り、読まなくていい、学ばなくていい分野は上記に挙げた学問のようです。
特に哲学、心理学はかなり怪しい学問だと考えているようです。
11 人文学と仕事と教養のマトリクス図
「人文学は「今=危機の時代」にこそ必要だ」という記事がありました。
https://toyokeizai.net/articles/-/91858
著者の内田樹氏の主張によると、「人文学は平時には役に立たない学問」ですが、「混乱期には役立つ時が来る」といいます。
また、多様性を確保しておくことは、「人類が生き延びるには重要だ」といいます。
さらに、実学は即効性がありますが、見ているスパンが短いの対し、人文学は役立たないと思われていますが緊急時には役立ち、見ているスパンも長いといいます。
そして、内田樹氏は「人文学と実学はお互いに交代して輝くから補完し合えばいい」といいます。
僕は、実学>人文学などの教養 路線です。
「7対3ぐらいでいいのでは?」と考えています。
政治家や教養で食べている1%未満の人は、この比率は逆転するでしょう。
実学である理系は人類に大いに貢献し、食わせてきました。
今後も理系の分野は拡大余地のある分野が目白押しです。
人工知能、ロボット(介護、交流、ドローンなど多数)、自動運転、IPS細胞、量子コンピュータ、パワードスーツ、エネルギー系などいくらでもあります。
対して、人文学の拡大余地はどれくらいあるのでしょうか?
人類の意識・心理を解明することか、資本主義に代わる思想、「人間はどう生きるべきかなどの倫理や正義」ぐらいではないでしょうか。
文化、宗教、言語、哲学などはそこまで変化しません。
グローバルに対応するために文化、宗教、言語は残してもいいでしょう。
しかし、人文学は拡大余地が少ないのです。
よって、貢献度も少ないです。
貢献度が少ないのなら多様性確保のため、念のため残しますが少数でいいのではないでしょうか?
また、哲学は学問としては終了している感がありますが、生き方や人生観を確立するための「哲学」という言葉には意味があります。
そのための哲学とは、「人間について深く知り、どう生きるべきかを徹底的に考える学問」というわけです。
そこには絶対の正解はありません。
人生は選択の連続であり、その選択の精度を上げるためにも自分の生き方や人生観としての哲学が必要なのです。
生き方としての哲学は大量の読書や経験を通じて培われるものです。
その人の思想や信条や価値観です。
その人が選択をする際の判断軸になります。
これは哲学という学問を学んだからといって、即効的に出来上がるものではないでしょう。
参考にはなるかもしれませんが。その人の生き様ですし、正解はないのです。
出世しやすい生き方などの哲学はあるとは思います。
生き方としての哲学を確立するためには哲学という学問を学ぶより「論語」や「孫子の兵法」や「君主論」を読んだ方がいいかもしれません。
しかし、哲学が役立つ分野があることが最近、分かりました。
人工知能の分野です。
詳しくは「人工知能のための哲学塾」を読んでもらえたらと思います。(半分理解できれば良い方でしょう)
そして、危機の時代こそ実学が役立ちます。
エネルギー問題、食糧、資源(レアメタル含む)などの危機を人文学が救えるとは思えません。
全て、技術が解決するでしょう。
介護も高齢化問題もロボットの出番です。
つまり、混乱期の今はエネルギーなどの大問題が解決しない限り、長く続き、その間は実学の出番なのです。
人文学ではありません。
人文学の出番は混乱期が終わった後でしょう。
その時に「人間とは何か?」の本質を問う余裕が出てくるかもしれません。
人文学は混乱期に必要でもないし、優先順位も低いですし、多様性の確保のため残されていますが、活躍する出番もないかもしれません。
人文学などの教養は再考、再編されるべきだと思います。
生き方や人生観としての学問ではない哲学については必要ですよ。(人工知能に関しては哲学は役立つようです)
橘玲氏の本を少なくとも大学関係者は読んで、パラダイムの転換についていくべきでしょう。
最後に、以下のマトリクス図を作ります。
1 「仕事ができる、教養がある」
2 「仕事ができる、教養がない」
3 「仕事ができない、教養がある」
4 「仕事ができない、教養がない」 です。
1と4は分かりやすいですよね。問題は2と3です。
「仕事ができる、教養がない」人達はビジネスマンに多いでしょう。
つまり実学中心派です。
対して「仕事ができない、教養がある」人達もいるでしょう。
仕事ができないとはビジネス系や民間のことであり、教養はあるのですから、学者系や教養で食っている人達になるでしょうか。
教養で食うのは仕事ができるといえば、教養での仕事はできるのでしょうが、ビジネスや民間ではおそらく通用しないと思います。
「仕事(民間)ができない、教養がある」人達が教養擁護派であり、厄介な人達です。
「仕事(民間)ができる、教養がある」人達はスーパーマンです。(この人達は教養もある程度、重視しますが、実学寄りだと思います)
そもそも、仕事を一生懸命にやっていたら、つまり実学をやっていたら、教養を学ぶ時間は限られます。
教養にばかり時間をつぎ込める人は、教養で食っていける人達か、実学にあまり力を注がない、つまり「民間での仕事ができない人達である可能性が高い」と思います。
マトリクス図の話題はこの辺で。
ではこの辺で。(4208文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。
「未来予測の超プロが教える本質を見極める勉強法」
「「読まなくてもいい本」の読書案内」
「人工知能のための哲学塾」
「トップ1%に上り詰めたいのなら、20代は残業するな」